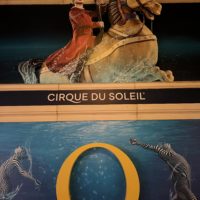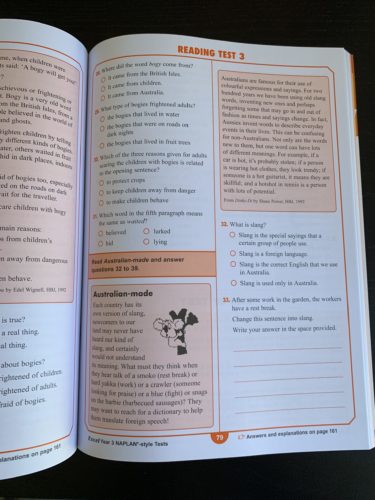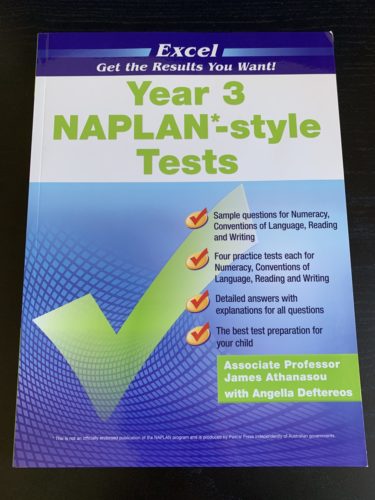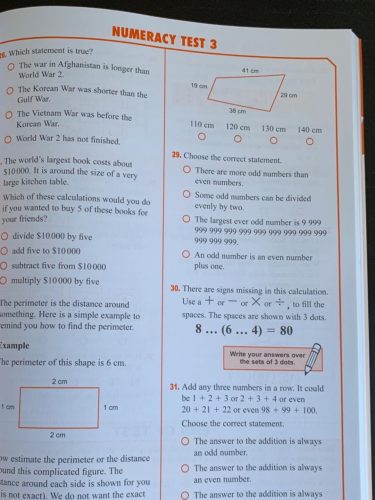皆さん、こんにちは。TAKEOFF Gold Coastの犬飼です。
さて、今年の夏休みプログラムも無事に終盤です。団体プログラムは、例年以上に学校側の内容も良く、参加してくださった皆さんも充実した表情で帰国されました。
今年は、初の試みとして、10月に7泊9日間の小学生向け現地校留学プログラム(すでに満員)を予定しておりますが、年末年始は留学の受け付けをしておりません。
次の募集は、2024年春休みです。
そんな中、お問い合わせでももっとも多い「ホームステイ」についてここに書き記しておきます。
多民族国家・移民の国であるオーストラリアにおいて“オーストラリア人”とは
留学の希望者から最も多い質問や要望は、やはりホームステイに関すること。
「ホームステイ先はいくつかの選択肢から自分で選べますか?」
「ホストファミリーが気に入らなかったら変えてもらえますか?」
「オーストラリア人(白人)の家にしてください」
「中国やフィリピンやインド系のファミリーはやめてください」
「シングルマザーの家は拒否します」
と言った類のものです。
皆さんのお気持ちはよくわかります!!
しかし、これらのリクエストは、オーストラリアの法律では人種差別として処罰の対象となります。
Anti-Discrimination Act 1991 – SECT 124A
124A Vilification on grounds of race, religion, sexuality or gender identity unlawful 124A Vilification on grounds of race, religion, sexuality or gender identity unlawful
(1) A person must not, by a public act, incite hatred towards, serious contempt for, or severe ridicule of, a person or group of persons on the ground of the race, religion, sexuality or gender identity of the person or members of the group.
もちろん、このブログで、法律や人種差別という話をしたいわけではありません。
むしろ、私も日本から子どもを留学に送り出すのであれば、真っ先に同じようなことを考えたと思いますし、島国で単一民族国家で暮らす日本人の場合、肌の色や目の色、髪の色が違うことを当たり前に認め合える環境にいないため、<英語圏=白人社会=留学>と言った根強いイメージはあると思います。
話しはそれますが、私が大学生の時にカナダへ短期留学した際、受け取っていた資料に記載されていたホストファミリーの名前は、KevinとGrace夫妻に息子はJamesでした。
家族写真は受け取っておらず、空港でKevinとGraceとの夢の対面を想像していた私に、「Hi, Tomoko」と声をかけてくれたのが、笑顔の(見た目)中国人一家でした。
私は、呼ばれて振り向いたまま、固まっていたと思いますし、様々な感情で混乱していました。
「カナダ人(勝手に白人をイメージ)…じゃないの?」
「騙された!(誰も騙していない)」
「カナダまで来て私、中国人の家にホームステイするの?」
何と言われようと、これが、この時の私の正直な気持ちです。成人式に着物を買う代わりに、両親に送り出してもらった貴重な4週間の短期留学…
私は、カナダが多民族国家で移民大国であることを知っていたつもりでしたが、それはそういった事実を知っていただけで、それが現実的にどういうことなのかという想像には事足りていませんでした。
ホームステイ先につくと、自宅は立派な西洋風の建物でしたが、中に入ると、中華街でよく見るようなアジアン装飾のリビング。そして、カナダのホームステイ先で最初の夕食は、麻婆豆腐でした(お父さんがお肉屋さん)。
思い描いていたホームステイのイメージとは180度違いました。
しかし、後からわかったことですが、彼らは移民二世・三世で、カナダで生まれ育ち、カナダの国籍、つまりカナダのパスポートを持っていました。彼らは、ルーツは中国でも、ナショナリティとしては「カナダ人」なのです。
もちろん、英語の面でも、彼らの第一言語は英語。どこを切り取ってもネイティブです。
もし、皆さんが誰かを「○○人」だと認識するとき、それは見た目でしょうか。国籍(パスポート)でしょうか。
同じようなことが、ここオーストラリアでも考えられます。
日本人を含むたくさんの移民がこの地で暮らしています。生まれも育ちもオーストラリアで、人種としての母国に一度も行ったことがない人たちもたくさんいます。私の周りにも、ルーツは日本だけど日本を知らない「日系オーストラリア人」はたくさんいます。
そのような「○○系オーストラリア人」も「ホストファミリーをしたい」と考えることは自然です。「あなたは見た目がアジア人なので、ホストファミリーには認められません」と言えません。
ペットの有無や、アレルギーの件、家族構成として子どもの有無、趣味や生活スタイルについては、希望をお聞きしながら調整することはできても、ファミリーの「人種」を問うことは絶対にできないのです。